15 Apr 2020
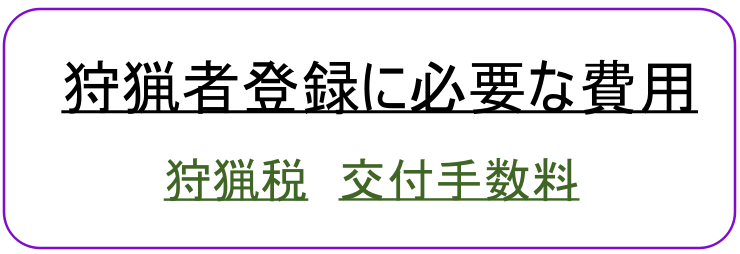
この記事では次のことを説明しています。
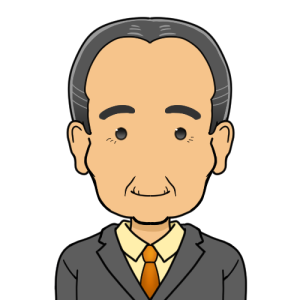
・狩猟者登録とは?
・狩猟者登録等に掛かる費用
・一猟期に必要な費用
狩猟者登録とは?狩猟免許を持っているだけでは猟はできません!
狩猟者登録は、狩猟を行うために必要な手続きです。
下記に一般的な手続きの流れを示します。
1. 登録申請書の準備
狩猟者登録を行うには、まず「狩猟者登録申請書」を準備する必要があります。
この申請書には、以下の情報を様式に基づいて記入します。
・住所、氏名、生年月日
・所持している狩猟免許の種類
・使用する猟具の種類
・狩猟免許の番号および交付年月日
・猟銃の所持許可証の番号など
2. 必要書類の提出
申請書とともに、以下の書類を提出する必要があります。
・申請者の写真(無帽、正面、上三分身、無背景のもの)
・狩猟免許のコピー
・その他、都道府県によって指定された書類
狩猟免許は、全都道府県に有効です。
ただし、狩猟を行いたい場所を管轄している都道府県知事に対し、狩猟者登録の申請をする必要があります。
狩猟者登録等に掛かる費用
かかる費用は下表のとおり、狩猟免許の種別によって異なります。
| 免 許 種 別 | |||
| 項 目 | 第1種銃猟 | 第2種銃猟 | わな・網猟 |
| 狩猟税 | 16,500円 | 5,500円 | 8,200円 |
| 手数料 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 |
| 計 | 18,300円 | 7,300円 | 10,000円 |
※1
第1種銃猟免許;県民税の所得割の納付を要しない者11,000円
※2
手数料;都道府県によって異なる場合があります。
※3
手数料および狩猟税の納付は、登録する都道府県ごとに必要となります。
上記以外にかかる費用として下記があります。
猟友会費
■猟友会とは
猟友会は、日本における狩猟者の団体であり、全国の都道府県に設置されています。
この団体は、狩猟免許を持つ人々を会員として受け入れ、狩猟活動の促進や野生動物の管理を目的としています。
■組織構成
猟友会は、各都道府県に「都道府県猟友会」があり、
その下に市町村単位の「支部猟友会」や「地区猟友会」が存在します。
これにより、地域ごとの狩猟者が集まり、情報交換や射撃練習などの活動の支援を行っています。
また、狩猟者登録や狩猟免許試験受験申請などの事務処理等を代行してくれる猟友会もあります。
■加入条件
猟友会には、狩猟免許を持っている方であれば誰でも加入することができます。
会員になることで、狩猟に関する情報や技術の習得、仲間との交流が可能になります。
■猟友会費について
・大日本猟友会費(共済金)
猟友会の上部組織である大日本猟友会への納付となります。
・第一種銃猟;4,800円
・第二種銃猟;2,300円
・都道府県猟及び支部会費
(神奈川県、某支部の場合)
・県会費 : 7,000円
・支部会費 : 3,000円
※新規に入会の場合、入会費 3,000円
以上の費用は狩猟を行う場合、毎年必要になります。
上記、以外に掛かる費用としてはハンター保険(任意保険)があります。
ハンター保険は、個人では加入できない場合があるようです。
なお、猟友会に入会しておれば、団体保険として加入できます。
また、有害鳥獣駆除に参加する場合、自治体によって保障の下限が(2億円とか)決まっているところもあります。
猟友会への加入は義務付けられているわけでありませんが、加入によるメリットは大きいです!
具体的には(支部によりけりではありますが)、
・狩猟免許の更新時期が近づくと葉書等で連絡してくれる。
・所持する銃の更新時期が近づくと葉書等で連絡してくれる。
・狩猟免許更新や銃の更新に関する申請書類の作成を代行してくれる。
・実猟で使用する実包の無許可譲受け証がもらえる。
これ、大きいです!
■ 無許可譲受け証とは?
実包を譲り受けるためには、原則として都道府県公安委員会の許可が必要です。
この許可を得るために申請し、交付されるのが「猟銃用火薬類等譲受許可証」です。
申請は、住所地を管轄する警察署の生活安全課で行います。
申請時には、猟銃・空気銃所持許可証や狩猟者登録証などの書類が必要になります。
譲受許可証には、譲り受けることができる火薬類の種類、数量、有効期間などが記載されています。
実包を譲り受ける際には、この許可証を火薬類販売業者に提示する必要があります。
2. 猟銃用火薬類無許可譲受票
狩猟者の利便性を考慮し、一定の条件を満たす場合に、許可なしで実包を譲り受けることができる制度があります。
この際に用いられるのが、一般的に「猟銃用火薬類無許可譲受票」と呼ばれる書類です。
この無許可譲受票は、通常、都道府県猟友会やその支部が交付しています。
例外的に警察署長が交付する場合もあります。
無許可で譲り受けることができる実包の数量には上限があり、例えば、1回の狩猟期間または鳥獣捕獲許可期間内で、散弾銃用実包とライフル銃用実包の合計で300個まで(ライフル銃用は50個まで)といった制限があります。
無許可譲受票を使用して実包を譲り受ける際には、猟銃・空気銃所持許可証狩猟者登録証または鳥獣捕獲許可証などを火薬類販売業者に提示する必要があります。
実猟で消費する実包の量って、たかが知れてますよね。
1日山歩きしたって一発も撃たないことって結構あります。
そんな、実猟で使用する実包のために警察署に行く手間を思うと、・・・ですよね。
・狩猟者登録申請を代行してもらえる。
住所地以外の都道府県を申請するとなると、これも結構大変!
・ハンター保険加入の事務処理を代行してもらえる。
・有害鳥獣駆除従事のとりまとめ。
等々。
猟友会に加入するメリットまとめ
✅ 書類の代行提出
✅ 銃・免許の更新通知
✅ 実包の譲受け証発行
✅ ハンター保険の加入代行
✅ 地域の駆除案件の紹介 など
狩猟者登録申請書の様式
狩猟登録申請書の様式は各都道府県のホームページからダウンロードできます。
ファイル形式は、wordかpdfとなります。
ダウンロードできない場合は、都道府県庁の該当窓口に行けばもらえます。
まとめ
狩猟者登録に必要な費用は、
・狩猟税(免許の種類別、それぞれの課税されます。)
・交付手数料(申請する免許毎に必要)
・ハンター保険
以上、狩猟する限り毎年発生かつ狩猟する都道府県毎に発生
となります。